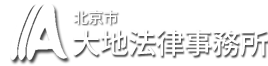企業が採用時に留意すべき「トラブルメーカー」
先日、入社数日後に「契約解除を強要された」として半年間で11社に対する労働仲裁を申し立てた女性の事例が話題となりました。この女性が「録音·録画」のためにペン型ボイスレコーダーなどを準備していたことから、裁判所はこれを悪意ある訴訟または「トラブルメーカー」であると判断し、その請求を棄却しました。
当該事件は、食品分野の悪意ある「プロクレーマー」行為と類似しています。実務上、ほとんどの新入社員は信義誠実の原則を守って入社しますが、『労働法』の保護を濫用して頻繁に仲裁を申し立てたり、虚偽の訴えを起こす「トラブルメーカー」が企業から不当に利益を得ようとする事件も一部存在します。
こうした行為は会社の利益を直接損なうだけでなく、会社の生産経営と信用にも悪影響を与える恐れがあるため、採用や雇用過程におけるリスク防止の強化は必須であり、採用調査や入社審査に十分留意することが求められています。
1.採用調査の実施
故意の「トラブルメーカー」を防ぐ最前線は採用段階です。一部企業は採用時に応募者(特に企業が採用予定の従業員)の過去の職歴や離職原因などを含む採用調査を実施しており、特に労働仲裁や訴訟および労働紛争の原因に関わったことがあるかどうかをチェックしていますが、これは効果的な方法であるといえます。
一部メディアの報道によると、一度労働仲裁に関わった従業員は再度労働紛争を引き起こす確率が高いとされています。この種の従業員は往々にして法律の抜け穴に精通しており、他の従業員を紛争に巻き込むことで企業リスクを増大させる可能性もあるため、採用予定の従業員が過去に労働仲裁や訴訟事件を起こしているかどうか、またはその紛争の原因や職歴などを事前に調査することが推奨されます。
2.「入社声明」への署名
採用調査だけでは従業員の過去の紛争や争議を完全には把握できないため、該当する従業員に対し、過去に紛争経験がないことを示す「入社声明」への署名を求める企業もあります。入社声明には以下のような内容が記載されています。
(1)元の雇用主との賃金や賞与およびその他経済問題はすべて決済済み。
(2)元の雇用主との間に未解決の労働仲裁や訴訟またはその他法的紛争は存在しない。
(3)虚偽の陳述により企業が損失を被った場合、相応の法的責任を負う。
入社声明への署名により、従業員の過去のトラブルによる関連リスクの低減が可能となります。同時に紛争発生時に企業に一定の法的保障を提供するものとなるため、「トラブルメーカー」に対してある程度の抑止力にもなりますが、署名を求める際は紛争原因を確認する必要があります。企業は紛争原因を区別せず一概に従業員を否定してはなりません。
3.「トラブルメーカー」の常套手段
「トラブルメーカー」による在職中の行為にも警戒が必要です。「トラブルメーカー」の主な手口としては悪意ある病気休暇申請、虚偽の労災報告書提出、解雇事由を故意に作り出すことなどがあります。ごく少数とはいえ、一部の従業員がこうした行為を常套手段としているのも事実です。また、これら行為には以下のような特徴が見られます。
(1)病気休暇を頻繁に取るが、適切な医療証明を提出できない。
(2)労災報告に疑問点がある、または明らかに事実と一致しない点がある。
(3)消極的サボタージュにより企業の違法解雇を誘導する。
「予防は治療に勝る」という言葉の通り、雇用リスクの管理制度を事前に整えることは、仲裁や訴訟などの事後処理よりはるかに重要です。こうした雇用リスクに備え、現地弁護士に内部規則制度の評価を依頼し、病気休暇審査プロセスの厳格化や労災認定手続きの規範化、従業員ファイルの作成など、コンプライアンスに準拠した対応スキームを制定することも重要です。
◆日系企業へのアドバイス
労働仲裁によって従業員がその権益を主張することは、法律で与えられた権利でもあります。そのため、単純にこれを理由として従業員の就業を拒否した場合は就職差別を疑われる可能性があることにも留意する必要があります。
悪意ある労働者による被害を避けるためには、コンプライアンス意識を高め、雇用管理の合法性と規範性を整備することが重要となるため、現地の弁護士に自社のコンプライアンス制度の審査や修正を依頼することも必要となるでしょう。
作成日:2025年09月16日