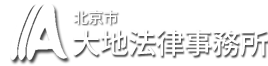朗報:育児補助制度実施方案を発表
7月28日、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁は「育児補助制度実施方案」(以下「本方案」という。)を発表しました。本方案は2025年1月1日を基準に適用されます。
本方案は、少子高齢化の現状に対し、子育て世帯に一定の現金補助を行うことで、出産を支援・奨励する制度を充実させるという国の方針を実現するための政策となります。そこで今回は、本方案の対象者や補助の基準について簡潔に解説いたします。
1.対象者の範囲
本方案では、2025年1月1日以降に出生した3歳未満の乳幼児を対象としており、3歳以上の幼児は対象外となります。(方案第2条第1項)
また、2024年12月31日までに出生した3歳未満の幼児もこの育児補助金の対象となりますが、補助金の支給月数は2025年以降の月数のみとなります。例えば、2022年6月10日生まれの3歳児の場合、2025年6月9日時点で請求可能な月数は6ヶ月となります。
2.育児補助の基準
本方案によると、育児補助金は年単位で支給され、現時点での支給基準は子ども1人あたり年間3,600元です。また、育児補助金は子どもの人数に関わらず(中国では夫婦1組あたり3人まで)申請することができます。
育児補助金は個人所得税が免除されるため、3歳未満の乳幼児を持つ人々にとっては朗報となります。(方案第2条2項)
地域によって経済発展の程度などが異なるため、補助基準にも多少差異がある可能性がありますが、原則的に同一の行政区域であれば政策や支給基準は同じです。(方案第6条)
3.その他の留意点
国務院が本方案を発表したことを受け、今後、各省の政府当局が地域の経済発展状況や人口動向、財政状況などを考慮し、具体的な実施計画を策定することになります。補助の基準や支給時期は、各地方の政策に基づきますので、各地域の政策の実施状況に注目する必要があります。
また、育児補助金は行政当局から自動的に支給されたり、企業が負担したりするものではありませんので、支給対象者の保護者が所在地の行政当局に自ら申請する必要があります。企業も所在地の地方政府が定める育児休暇や介護休暇について正しく理解し、各地の規定通りに実施する必要があります。
この育児政策は個人所得税特別控除、育児サービス、出産休暇などの政策と連動しており、少子高齢化への対策として位置づけられています。今後、母子関連消費や育児サービス、小児医療、乳製品などの各分野の市場が拡大することが予想されますので、関連日系企業もこうした動向に注目することが重要となるでしょう。
作成日:2025年07月30日