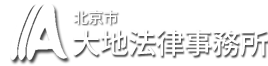新情報:労働争議に関する司法解釈(二)の重要な変更点 その1
2025年8月1日、最高人民法院は記者会見を開き、『労働争議案件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の解釈(二)』(以下、『解釈二』)およびその典型事例を発表しました。『解釈二』は全21条から成り、2025年9月1日より施行されます。
本『解釈二』は、労働仲裁委員会および裁判所が労働争議に関する事件を審理または裁決する際の全国的な細則として、企業と従業員間の権利義務に大きな影響を与える内容であるため、大きな注目を集めています。
そこで今回は、『解釈二』の主な内容から、企業が注意すべき要点をシリーズで簡潔に紹介いたします。
1.「社会保険加入の放棄を承諾」した場合でも、経済補償請求が認められる可能性
実務において、会社と従業員が「社会保険に加入しない代わりに現金を支払う」という合意を行うことがあります。このようなケースでは、従業員が「社会保険未加入」を理由に労働契約を解除し、経済補償を請求したとしても、一部の地域(例:山東省、浙江省)の裁判所では、従業員の誠実義務違反を理由として、請求を認めない判断を下していました。
しかし、今回の『解釈二』では大きな方針転換がなされており、従業員が「社会保険に加入しない」と事前に承諾していた場合でも、その後「社会保険未加入」を理由に契約を解除し、経済補償金を請求した場合、裁判所はこれを支持する立場を示しました。これにより、企業側の雇用リスクとコスト(社会保険の追納+延滞金+経済補償金)が大幅に増加することになります。(『解釈二』第19条)
なお、企業が法に基づき社会保険料を追納した場合は、従業員に対し、すでに現金で支払った分の返還を求めることが可能です。また、この『解釈二』の施行前後を問わず、「社会保険に加入しない」という合意は無効であり、従業員は人力資源・社会保障局等に苦情を申し立て、企業に追納を求めることができます。
2.「定年退職後の再雇用者」と企業は必ずしも労務関係ではない
これまで、中国ではすでに年金を受給するか退職金を受け取った定年退職者を再雇用し、その後雇用に関するトラブルが発生した場合、裁判所は企業と再雇用者の関係を「労務関係」として処理していました。中国では、「労務関係」には民法典などの民事法が適用され、「労働契約法」上の賃金や残業代、社会保険、病気休暇、経済補償などの規定は原則として適用されません。
しかし、今回の『解釈二』ではこの規定が削除されました。つまり、年金を受給している定年退職者が再雇用された場合でも、その関係が一律に「労務関係」と判断されるわけではなく、一部の内容については労働法の規定が適用される可能性があります。(『解釈二』第21条)
今後、再雇用者が残業代の支払いや労災保険の加入を求め、労災が発生した場合には、企業がその一部(例:休業中の給与など)の負担を求められるケースが出てくる可能性があります。また、2025年7月31日に人力資源・社会保障部が発表した「高齢労働者の基本的権益保護に関する暫定規定(パブリックコメント案)」にも、同様の方向性が示されています。
◆ 日系企業へのアドバイス
『解釈二』には上記の重要な変更点以外にも、企業の雇用管理に大きな影響を与える以下のような規定が多数含まれています。
•関連会社による混同雇用
•競業避止条項
•外国人との労働関係の認定
•労働契約書未締結による2倍の賃金支払い義務
•勤務期間違反による損害賠償
•労働仲裁における時効の抗弁など
そのため、労務関連のリスクを回避または軽減するためには、企業の人事部や総務部、経営陣が本『解釈二』の内容を正しく理解し、自社への影響を分析し、必要な場合には現地の弁護士と連携して対応策を検討することが重要となるでしょう。
作成日:2025年08月07日